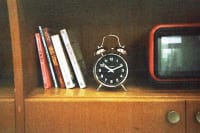仕事ができない人の特徴・コミュニケーションと視点が大事

引用: https://res.cloudinary.com/macm/image/upload/v1543677251/i3my5gbysxtogetsxxvz.jpg
なぜできないのか?どうしてできないのか?
部下や同僚などと仕事をする上で、誰しも経験するのが、このような仕事のできない人との共同作業ではないでしょうか。
実はその悩みの多には、コミュニケーションの方法や視点を変えることで解決への道が開けることができます。

引用: https://res.cloudinary.com/macm/image/upload/v1543677294/de1u8eoddnvul2xvvaoh.jpg
また最近増えている傾向としてよくある悩みが上司で仕事ができない人。
年功序列制を設ける古い体質の企業はまだまだ多くあり、さほど能力が無くても管理職になるケースもよくあります。
そのような場合においては、いかに的確なコミュニケーションで対処するかが重要なポイントになります。
仕事ができる人には上司をうまくコントロールできるコミュニケーション能力を武器にし、仕事を要領良くテキパキこなす人が多くいます。
今回は「仕事ができない人」への改善方法を通して、解決へのキーとなるコミュニケーションと視点の置き方についても詳しくお伝えしていきます。
仕事ができない人の特徴【分析①】応用が利かない

同じ内容、似た内容の業務であれば機転を利かし、調べながら進めることができますが、定型的な業務しか考えが及ばす
、従来と少しでも違う内容を振られた場合、わからなくなり、都度指示を出さなければ仕事を前に進めることができない人がいます。
実は、このような人たちの多くは、仕事を行う視野に「自分で考える」ことが欠けてることが多く、言われた通りに行うことには長けていますが、定形外の仕事を振られると思考停止してしまうのです。
関連記事
仕事ができない人の特徴【改善法】応用が利かない
相手の能力に合わせて、分割して指示を出す
即効性のある手段としては、定型的な作業になるようにフローを分割すれば解決する場合があります。
但しこの方法は、あくまでも一時的な手段なので、レベルアップを目的とした指導には向いていません。
ですので、短期的な共同作業などに向いた方法です。
業務に必要な基本知識を理解させる

指示待ち型や定型業務ばかりを好んで行う人を指示する場合、何のためにする作業なのか目的を把握していないことが多くあります。

業務説明する際に、目的をしっかり伝えて「考えながらやる」ことを習慣づけることで、要領を見つけるきっかけづくりにもなり理解度も高まります。
仕事ができない人の特徴【分析②】上司の指示が下手

指示がわかりづらい上司は「仕事ができる上司」に加え、「仕事ができない上司」である場合もありえます。
部下や同僚は注意することができますが、上司とあってはなかなかそうはいかず、悩む人も多いのではないでしょうか
実は、上司の特徴を良く理解して、それに相応した応対をすることで、ストレスを軽減しお互いに良い関係を築きあげることにも繋がります。
仕事ができない上司
例えば年功序列により能力以上の出世を遂げた上司で、業務内容を全く把握しておらず決定権だけ委ねられている場合です。
もしあなたの上司がそうだった場合、コミュニケーションはできるだけ、メールで行うのがベストです。
決定権を持っている上司としては、自分に実力が欠けていることを自覚していますが、プライドは守りたいところです。
このような上司の判断ミスにより、必要な情報を部下に伝えていなかったなどと言うことも実際に良くある話です。
そのような場合、上司のミスが原因で被った損害も、自分のプライドを守るために、部下であるあなたのせいにされる可能性もあります。
そのような理不尽なことに巻き込まれないためにも、普段の業務のやり方でしっかり自己防衛はすることが肝心です。
仕事ができるが部下への指示が下手な上司

指示通り書類を作成したところ、当初の指示とは違うとダメ出しの山。
「だから違うんだよ!」と言われて悩むことも・・・。
このような場合、言うことがころころ変わり、「指示がちぐはぐ」、「話がころころ変わる」と感じるのではないでしょうか。
実はこの「ころころ変わる」の裏には、状況が変わり軌道修正を行ったため、指示内容が変わる場合に多くみられるケースです。
本人は説明不足の自覚がないため、部下が理解していると思い込み、どんどん突き進んでしまうことが原因です。

そのような上司を持った場合、疑問を持った段階で間髪入れず確認するなど、方法を変えていかなければ、あなたが上司に「仕事ができない人」「要領の悪い人」というレッテルを貼られる危険性があるので気をつけなければなりません。
関連記事
仕事ができない人の特徴【改善法】上司の指示が下手

上司とウマが合わない、あまり良く思われていないなど、上司との関係で悩む人も多くいるのではないでしょうか。
あなたの上司が理解ある上司であるならば、かなり恵まれているといっても過言ではありません。
長所が認められて出世した上司もまた一人の人間である以上、その短所も上手に受け入れることで、関係が改善され、良い方向に進む場合があります。、
ここでは先ほどのお伝えした対照的な2つのタイプの上司との仕事の進め方について解説していきます。
仕事ができない上司との仕事の進め方

上司の性格が良いにしろ悪いにしろ、その上司が関わることによって被った失敗などの自衛手段として、重要な報告は口頭のような後で確認できない方法はとらず、極力メールを使用し、普段からCCで更にその上の上司にも常に送る習慣をつけると安全です。
あなたの上司も自分の上司に内容を共有されているとなると、下手なことはできないな、という気持ちになり、理不尽なトラブルを未然に防ぐ防止策にもなります。
仕事ができるが部下への指示が下手な上司の対処法
実力が認められて出世した上司は、頭の回転も良く、本人が抱えている業務量も膨大なので、効率性を重視します。
自分のレベルと同等に、部下への指示も効率を優先させるため、やや指示が手荒だったりする場合もあります。
つまり、考えればわかることをわざわざ説明しない場合が多いということです。

ですので、あなたが考えてもわからないことは、効率性をもって口頭やメールなど適切な手段で質問し、軌道修正しながら経過報告していくと効果的です。
仮に上司が説明不足だた場合も気づくことができるので、お互い良い関係で効率よく業務を進めることができます。
仕事ができない人の特徴【分析③】ミスを繰り返す

入力ミス、連絡ミス、作業ミスなど作業によってミスの考え方もさまざまですが、仕事ができない人として良く見られるケースが、「同じミスを繰り返す人」です。
この「同じミスを繰り返す人」は、自分ではその原因を見つけることが困難な場合が多いことが問題点のひとつです。
また業務のジャンルによって向き不向きがあるので、適性に合わせて指示の方法を変えることも必要になります。
関連記事
仕事ができない人の特徴【改善法】ミスを繰り返す
思い込みを改善
ミスを繰り返す人に多い特徴が思い込みが激しいという点です。
そのような場合は自分だけでは改善が難しいため、客観的な視点をもってミスを防止させるため、さまざまな視点で作ったチェックシートの使用をおすすめします。
客観的な視点でチェックする

繰り返されるミス。
それは今、あなたの目の前のひとりの部下だけかもしれませんが、実は改善措置を設ける場合、より広く客観的な視点を向けることで、これからあり得るヒューマンエラーへの改善にもなります。
同じ仕事が繰り返され場合は、ミスを引き起こす原因をしっかり意識した作業工程をつくることが効果的です。
やってはいけないこと

一番やってはいけないことは、ミスの都度激しく叱責することです。
叱られて委縮してしまい、ミスの隠ぺいを招くからです。
仕事ができない人の特徴【分析④】仕事を抱え込む

仕事を抱え込む人の特徴のひとつが時間にルーズであることです。
共同作業に関わる場合には溜め込んだ業務を遅らせてしまうことで、全体の作業を遅延させ、悪影響を及ぼします。

仕事を抱え込む人のもうひとつの特徴はプライドが高く、たくさん仕事を抱えている自分は仕事ができる人だと勘違いしているところです。
実際には要領が悪いので、仕事が溜まる実態を人と共有して、事実と向き合うことで、解決へとつ繋げます。
関連記事
仕事ができない人の特徴【改善法】仕事を抱え込む
タイムスケジュールを共有する

仕事の抱え込みチェックとして、計画性を身に付けてもらうことが重要です。
他人に自分のタイウスケジュールを共有させることで、自らの業務の見直しをしざるを得ない状況を作ります。
プライドが高い人は、スケジュール通り全うしようとするので、良い方向へ転換していきます。
随時経過報告をしてもらう
タイムスケジュールを作成した上で定期的な経過報告もしてもらうようにすると効果的です。
常に進捗がチェックされる緊張感をもつことが、期限に間に合わせようという気持ちやプライドを刺激するので、様々な方法を駆使するようになり、要領良く業務を進めることに繋がります。
仕事ができない人の特徴【分析⑤】要領が悪い

要領が悪い人の特徴は、仕事の優先順位がわからず、何から手を付けて良いかわからない人です。
特徴としては、時間管理能力に欠けており、目につくところ、気になるところから取り掛かる傾向にあるため、そろそろ終わるころかな?という頃になっても悪銭苦闘しながら全開で仕事をしている人です。
任せた仕事がその人で完結するのであれば、大きな問題にはなりませんが、共同作業の中の一員の場合は、他の業務の遅延にも繋がり悪影響を与えます。
関連記事
仕事ができない人の特徴【改善法】要領が悪い

業務の全体像を把握させる
要領が悪い=時間管理ができない、と言って良いでしょう。
要領が悪い人には業務の全体像を把握してもらうことが早道です。
提出期限を細分化する
まずは提出期限を設けて、その人に見合う仕事の速さより少しタイトに設定します。
そのうえで、業務を細分化してフローを作り、業務フロー毎に提出期限を設定します。
期限を意識した業務サイクルがトレーニングとなり、徐々に要領を身に付けることができます。
仕事が気になる方はこちら!
まとめ

「仕事ができない人」は一見、迷惑な存在として見てしまいがちですが、視点を変えて見れば、全体の業務改善、または自分に振り返りを与える存在でもあります。
また指示や手段を変えることで「仕事ができない人」が驚くほどの成長を見せることもよくあることです。
ポイントは視点を変えること、そして複眼的な物の見方が、目の前の悩みを解決させてくれることになるのです。